退職時にデータ削除や嫌味メールなど、職場に迷惑をかける「リベンジ退職」が急増しています。調査では約1割の職場で被害経験ありとの結果も。今回は、最新事例とともに、リベンジ退職防止のための具体策5選をわかりやすく解説します。
「リベンジ退職」とは?最新調査でわかった衝撃の実態
「必要なデータをすべて消して退職」「嫌味が込められた一斉メール送信」「繁忙期を狙った退職」――
こうした報復型の退職が「リベンジ退職」と呼ばれています。
経営コンサル会社「スコラ・コンサルト」の最新調査(2025年5月実施)では、全国2,106人中、11.8%が職場でリベンジ退職を経験したと回答。実際の声は深刻です。
-
退職者が担当データをすべて削除し、復旧に数週間かかった
-
嫌味たっぷりのあいさつメールが全社員宛に送られた
-
書類をばらまいて音信不通で退職した
SNSでも「#リベンジ退職」がトレンド入りするなど、世間の注目度も高まっています。
なぜ「リベンジ退職」が急増しているのか?
リベンジ退職が増えている背景には、労働環境や価値観、SNS文化の変化が影響しています。
-
長時間労働や不公平な評価など、職場への不満が増加
-
転職市場の活発化により退職の心理的ハードルが低下
-
SNSで退職体験談が拡散され、「やってもいい」という空気が広がっている
特にSNSの影響は大きく、匿名で不満を発信しやすい環境がリベンジ退職を後押ししています。
実際にあったリベンジ退職の最新事例
ニュースで報じられたリベンジ退職の事例を紹介します。
-
データ全削除事件
元社員が共有サーバーから重要データを大量削除し、復旧不可能に。会社は約577万円の損害賠償請求を起こしたケース。 -
嫌味メール拡散トラブル
退職者が「ブラック企業から解放された」と全社員宛にメール送信し、スクショがSNSで拡散して炎上。 -
繁忙期狙い退職
年度末直前に主要担当者が退職し、社内プロジェクトがストップ。SNSに「ざまあみろ」と投稿し波紋を呼んだ。
企業にとっても社員にとっても、大きな損失を招くリスクがあることがわかります。
リベンジ退職を防止するための社員向け対策
感情的な退職ではなく、後悔しないキャリア選択をするために、社員が取るべき対策をまとめました。
冷静な判断をするための「冷却期間」
退職届を出す前に、少なくとも1週間は考える時間を確保しましょう。感情がピークの時は視野が狭くなりやすいため、冷静に判断する時間が必要です。
退職理由を明確にする
「給与への不満」「人間関係」「評価」など、原因を紙に書き出して客観視します。感情と事実を切り分けることで、より良い判断ができます。
信頼できる第三者に相談する
キャリアコンサルタントや家族、友人に相談し、客観的な意見を取り入れることで、退職以外の選択肢を見つけやすくなります。
企業ができるリベンジ退職防止策
企業も、従業員トラブルを防ぐための体制づくりが欠かせません。
社員とのコミュニケーション強化
-
定期的な1on1面談で本音を引き出す
-
匿名アンケートで職場の不満を把握する
-
離職予兆を早期にキャッチする仕組みを導入する
セキュリティ体制の強化
-
退職者のデータアクセス権を段階的に制御
-
業務データをクラウドで自動バックアップ
-
引継ぎマニュアルを整備し、混乱を最小限に抑える
こうした対策を講じることで、データ削除や嫌味メールなどの被害を未然に防げます。
まとめ
リベンジ退職は、職場への不満や企業体制の不備が重なったときに起こる現代型トラブルです。
防止のポイントは「早期の対話」「退職ルールの整備」「キャリア相談体制」の3つ。
感情的な退職ではなく、後悔しないキャリア選択を実現するために、社員と企業の双方が対策を取ることが重要です。
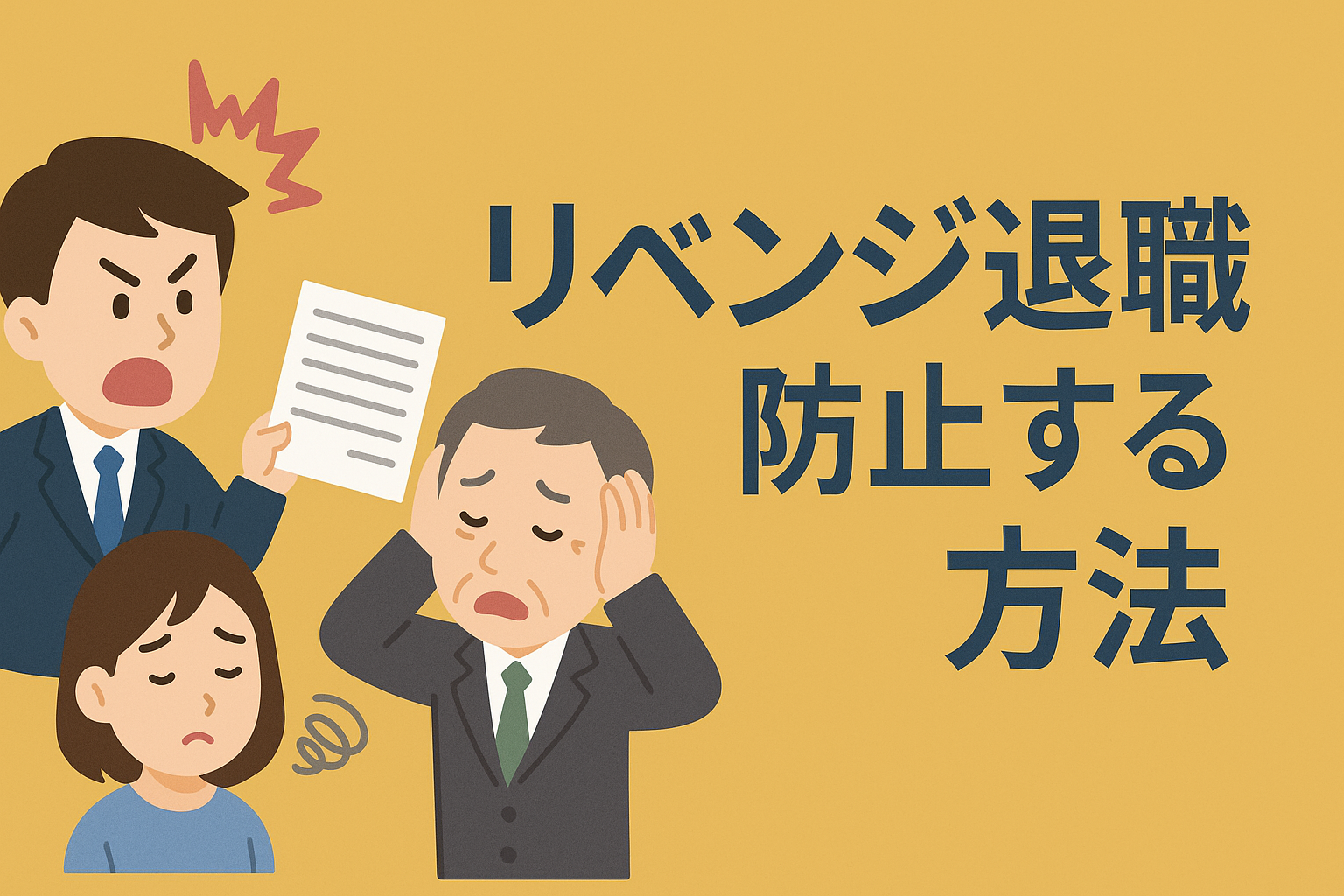

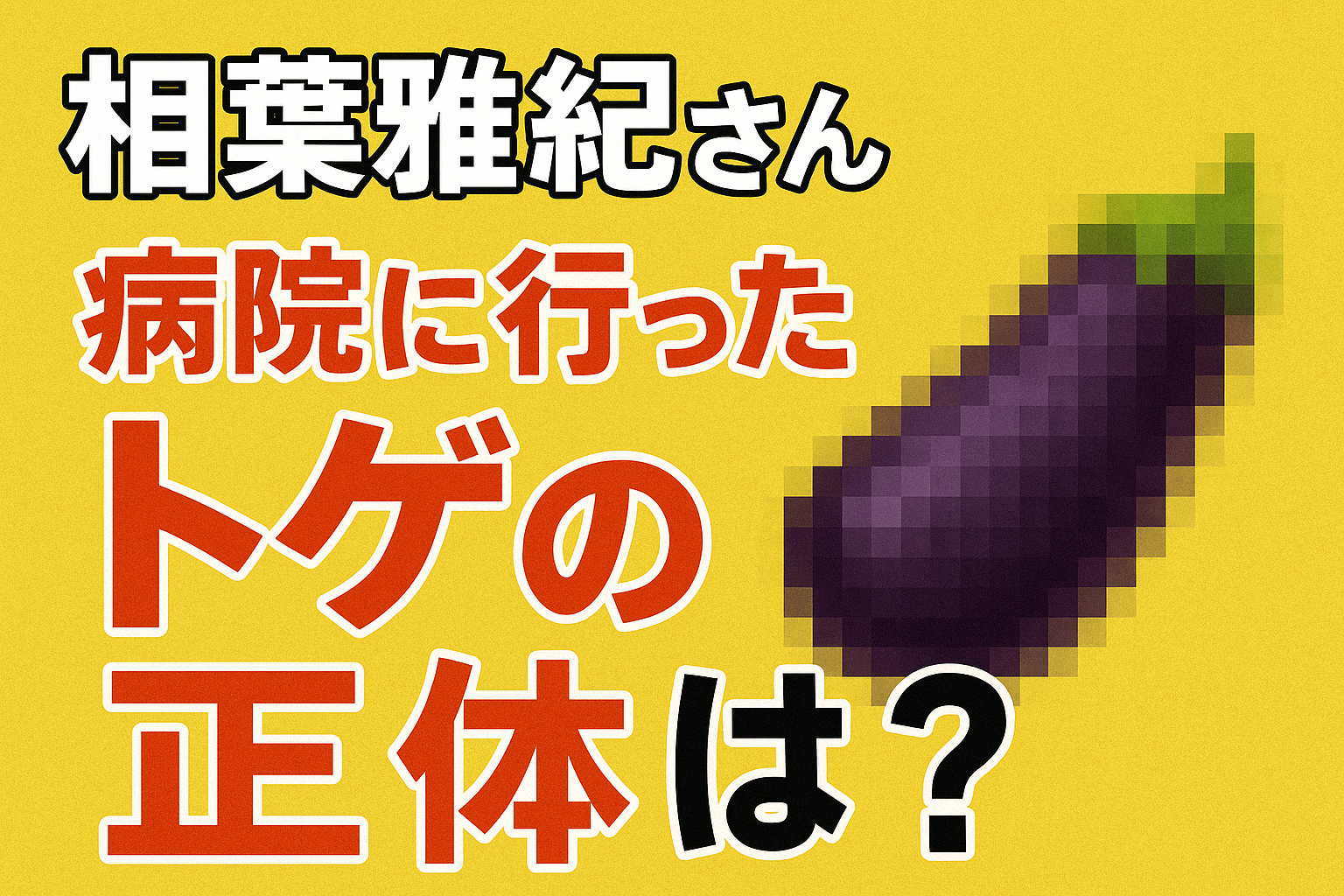
コメント