鈴木のりたけさんのプロフィール
絵本作家・イラストレーターの鈴木のりたけさん(1975年生まれ)は、静岡県浜松市出身。「しごとば」シリーズや「大ピンチずかん」など、ユーモアと温かみのある作品で幅広い世代から支持を集めるクリエイターです。会社員を経て独立し、現在は千葉市を拠点に活動しています。
鈴木さんには3人のお子さんがいます。長女は高校2年生、長男は中学2年生、次男は小学6年生です。
子どもたち3人が小学校から不登校を経験
鈴木さんの3人のお子さんは、いずれも小学校時代に不登校を経験しました。特に長女は小学校2年生のときに学校に通えなくなり、家族にとって大きな転機となったといいます。当時は家庭内が暗い雰囲気になり、親として深く悩む日々が続きました。
フリースクールへの通学と笑顔の回復
悩みながらも鈴木さん夫婦は話し合いを重ね、子どもたちの意思を尊重することを選びました。現在では、長女をはじめ長男・次男もフリースクールに通い始めています。その結果、家族の中に少しずつ笑顔が戻り、以前より穏やかな日常を過ごせるようになったといいます。
「待つ子育て」への気づき
当初は「学校に行くべきだ」という考えを強く持っていた鈴木さん。しかし、長女の不登校をきっかけに考え方が大きく変わりました。
「子どもは親の人生とは別の人生を歩む存在である」という認識に立ち返り、無理に学校へ行かせるよりも、子ども自身が自分のペースで考え、行動できるよう見守ることを大切にするようになったのです。
この「待つ子育て」は、親にとって簡単なことではありません。しかし、子どもが自分の気持ちを整理し、自ら動き出すためには、親が余白を与えることが必要だと鈴木さんは実感したといいます。
絵本に活きる子育ての視点
鈴木さんの代表作「大ピンチずかん」シリーズは、子どもの日常にある小さなトラブルや困りごとをユーモアたっぷりに描いた作品です。実は、この発想は家庭での子育ての中から生まれたものだといいます。
例えば、次男が牛乳をこぼした体験がきっかけで生まれたアイデアもあるそうです。日常の“ちょっとしたピンチ”を、笑いに変える鈴木さんの創作スタイルには、子育ての姿勢が反映されています。
不登校から得た家族の学び
鈴木さん一家は、3人の不登校を通じて多くの学びを得ました。
-
価値観の転換:学校に行くことだけが正解ではないと気づいた
-
「待つ」姿勢の大切さ:親が焦らず、子ども自身のタイミングを信じる
-
家庭の安心感を最優先に:家が子どもにとって安心できる場所であることを重視
-
創作への影響:子どもの日常が絵本の発想源となり、作品に活かされている
この過程で鈴木さんは、親としての価値観を見直し、子どもと向き合う時間を大切にするようになったといいます。
まとめ:正解のない子育てを前向きに捉える
鈴木のりたけさんの経験は、不登校に悩む家庭にとって大きなヒントとなります。
「世間の常識」ではなく、「自分たち家族にとっての幸せ」を最優先に考える姿勢は、多くの親に勇気を与えてくれるでしょう。
鈴木さんの子育ては、不登校を“問題”ではなく、親子の絆を深めるきっかけとして捉えています。
その柔軟な視点と「待つ」姿勢は、家庭をより穏やかで前向きな場所へと変える力を持っているのです。
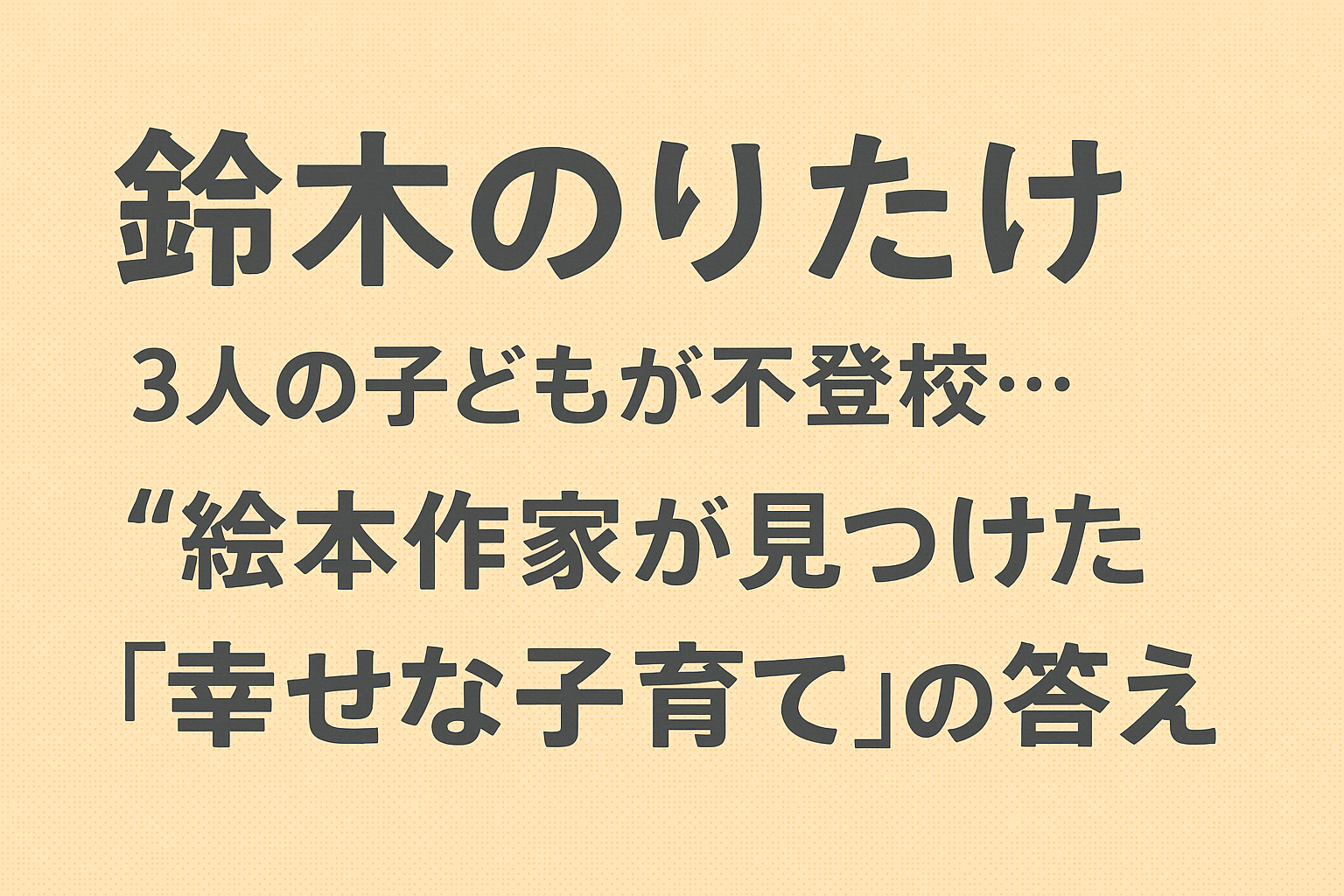
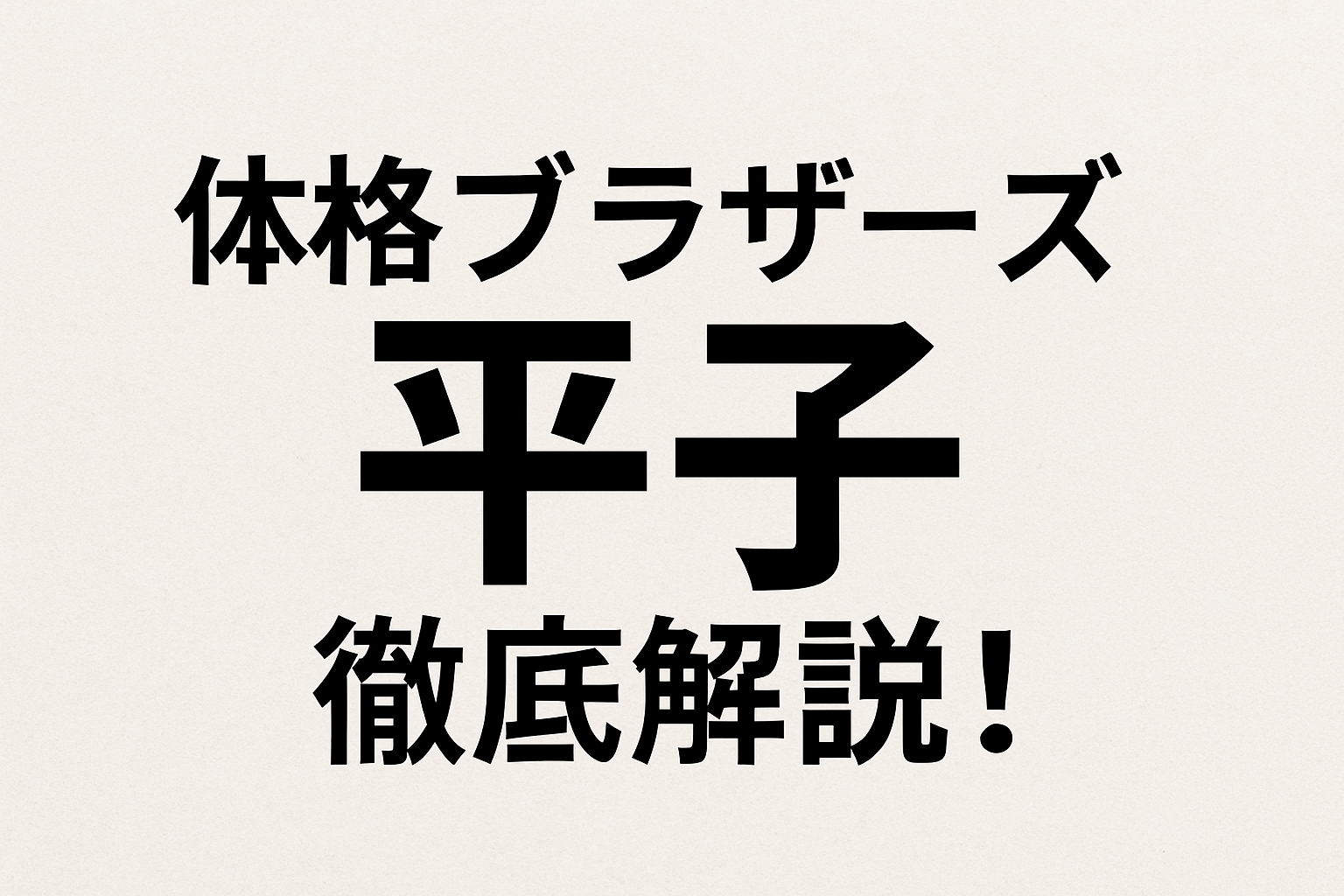

コメント